「ボリンジャーバンドって難しそう…」「順張り?逆張り?どっちで使えばいいの?」
そんな疑問を持つFX初心者の方へ向けて、本記事ではボリンジャーバンドの基本から応用テクニックまでを、プロ視点でわかりやすく解説します。
ボリンジャーバンドとは?FX初心者向けに仕組みと定義を解説
ボリンジャーバンドは、価格の変動幅(ボラティリティ)を視覚的にとらえるために開発されたテクニカル指標です。開発者はジョン・ボリンジャー氏。
この指標は、以下の3つのラインで構成されます:
- ミドルバンド:20期間の単純移動平均線(SMA)
- +1σ〜+3σ:価格の上限バンド(標準偏差)
- -1σ〜-3σ:価格の下限バンド(標準偏差)
±2σの範囲内に価格が収まる確率は約95%。この統計的な性質を利用して相場の行き過ぎや収束を読み取るのが特徴です。
ボリンジャーバンドとボラティリティの関係
ボリンジャーバンドはボラティリティ(変動性)をリアルタイムで視覚化してくれる便利なツールです。
- バンドが広がる:ボラティリティが高い(=相場が大きく動いている)
- バンドが縮む:ボラティリティが低下(=レンジ相場や様子見状態)
この「幅の変化」に注目することで、トレンド発生の前兆やエントリーのチャンスを掴みやすくなります。
ミドルバンド(SMA20)の役割
ボリンジャーバンドの中央にあるミドルバンド(SMA20)は、相場の平均的な価格を表します。
- 価格がミドルバンドの上にある → 上昇傾向
- 価格がミドルバンドの下にある → 下降傾向
このラインはトレンド判断の基準としても使え、他のインジケーター(MACD・RCIなど)との組み合わせでも効果を発揮します。
ボリンジャーバンドの基本的な使い方|順張り・逆張りの2パターン
1. バンドウォーク:順張り戦略
価格が+2σ付近に沿って上昇し続ける状態を「バンドウォーク」と呼びます。これは強いトレンド相場のサイン。
- ミドルバンドより価格が上にある
- +2σラインに張り付きながら推移
- MACDなどで勢いを確認できる
💡 実体験:私自身もバンドウォーク中に飛び乗ったことで、エントリー直後からスムーズに伸びた経験が何度もあります。トレンド時は素直に順張りが有効です。
2. バンドタッチ:逆張り戦略
価格が±2σや3σにタッチした場面で、「行き過ぎ」と判断して逆張りを狙う戦術。
- バンドが広がっているときは危険(トレンド中)
- バンドが狭まっている状態での反発を狙う
- RCIやRSIと併用してタイミングを見極める
⚠ 注意:トレンド発生中はそのまま突き抜けることも多く、逆張りのタイミングを誤ると損切りになるリスクもあります。
応用テクニック|ボリンジャーバンドのブレイク&スクイーズ戦略
ボリンジャーブレイク戦略
±2σを明確にブレイクした場合、それが新しいトレンドの起点になる可能性があります。
- スクイーズ(収縮) → エクスパンション(拡大)の流れに注目
- ローソク足が±2σを抜ける
- ミドルバンドが傾き始める
スクイーズからのエントリー
バンドが極端に収縮した後は、爆発的な動きが出やすくなります。
特に、レンジブレイク後の順張りが成功しやすいパターンです。
他のインジケーターとの併用例
ボリンジャーバンド単体ではなく、他の指標と組み合わせることで精度が上がります。
- MACDのゴールデンクロス × バンドウォーク → 順張り強化
- RCIの反転 × バンドタッチ → 逆張りの根拠
- 移動平均線との位置関係でトレンド方向を確認
よくある誤解と注意点
「バンドに触れた=反発」とは限らない
よくある誤解が、「±2σに触れた=必ず反転」という思い込み。
実際にはトレンド相場ではそのままブレイクして伸びるケースが多く、逆張り一辺倒は危険です。
時間軸による使い分けが重要
- 15分足では逆張りに見える
- 1時間足ではトレンド継続中
このように、複数時間足での確認が必須です。
まとめ|ボリンジャーバンドを使いこなすコツ
- 順張り・逆張りどちらにも使えるが、「環境判断」が鍵
- バンドの形状(収縮 or 拡大)を常にチェック
- MACDやRCIと組み合わせて相場を多角的に判断
ボリンジャーバンドは「難しい」と思われがちですが、慣れてしまえば非常に強力なツールになります。まずはデモトレードなどで感覚をつかみ、自分なりの使い方を見つけてみてください。
参考リンク
本記事の内容理解に役立つ公式サイトへのリンクです。



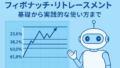
コメント