移動平均線×RCI×ローソク足の組み合わせ方|3つの視点で分析する応用ガイド
前回の記事では「ローソク足×RCI」の組み合わせを用いた分析方法を紹介しました。
今回はさらに一歩踏み込み、「移動平均線(MA)」も加えた3つの視点による応用型の分析手法を解説します。
この3つを組み合わせることで、トレンド方向・反転の兆し・タイミングを多角的に確認できるようになります。
この分析法の目的
- 無駄なエントリー判断を減らす
- 根拠が重なる箇所に注目する
- 順張り(MA)と勢い確認(RCI)を両立する
各インジケーターの役割
1. 移動平均線(MA)
移動平均線は、価格の平均的な推移を線で表すことで、トレンド方向を視覚的に把握できる指標です。
20EMAや75EMAなどがよく利用されます。
- 価格が移動平均線の上 → 上昇傾向
- 価格が移動平均線の下 → 下降傾向
2. RCI(Rank Correlation Index)
RCIは、価格と時間の関係性から相場の過熱感や反転の兆しを数値で把握するオシレーター系指標です。
- +80以上:買われすぎ(上昇が一服する可能性)
- −80以下:売られすぎ(下落が一服する可能性)
3. ローソク足
ローソク足は、相場参加者の心理を表す重要なチャート形状です。
特に反転や勢いの変化を捉える際に役立ちます。
- 陽線ピンバー:反発の兆し
- 陰線包み足:反落の兆し
3つの視点で見る分析の流れ
上昇傾向を確認する場合
- 価格が20EMAの上にあり、移動平均線が上向き
- RCI9が−80付近から上向きに転じる
- 直近のローソク足が陽線ピンバーまたは包み足
下降傾向を確認する場合
- 価格が20EMAの下にあり、移動平均線が下向き
- RCI9が+80付近から下向きに転じる
- 直近のローソク足が陰線ピンバーまたは包み足
このように、移動平均線でトレンド方向を、RCIで勢いを、ローソク足で市場心理を確認することで、より冷静な分析が可能になります。
チャート分析の一例
たとえば、以下のような状況では複数の要素が重なっていました:
- 価格は20EMAの上にあり、上昇基調
- RCIが−85から−70へと上向きに転じている
- 陽線ピンバーが出現し、反発の兆しを示唆
このように条件が重なった場面は、相場の変化点を客観的に捉えるうえで注目すべきポイントになります。
この分析法の特徴
- トレンド方向・過熱感・市場心理を一度に確認できる
- 複数条件を組み合わせることで判断の信頼性を高めやすい
- スキャルピングからデイトレードまで幅広く応用できる
活用時のポイント
- 移動平均線がフラットな場合は方向感が乏しいため、様子を見る判断も有効
- RCIの反転は確定足を確認してから判断する
- ローソク足のシグナルは押し目や戻り目など、節目で出現しているとより参考になる
リスク管理と注意点
- 損切りラインは直近高値・安値を参考に、あらかじめ設定する
- 利確ポイントはリスクリワード比など、事前に決めた基準をもとに管理する
- 条件がすべて揃っているかを客観的に確認してから分析を進める
まとめ:3つの視点を組み合わせて分析精度を高めよう
移動平均線・RCI・ローソク足の3点を組み合わせることで、方向性・勢い・市場心理を総合的に捉えられます。
これにより、分析の一貫性が高まり、感情に左右されにくい判断をサポートします。
まずはデモ口座などを活用し、実際のチャートで「移動平均線+RCI+ローソク足」を表示して観察してみましょう。
相場の特徴や動き方を理解することで、より自分に合った分析スタイルを見つけられるはずです。
参考リンク
本記事の内容理解に役立つ公式サイトへのリンクです。

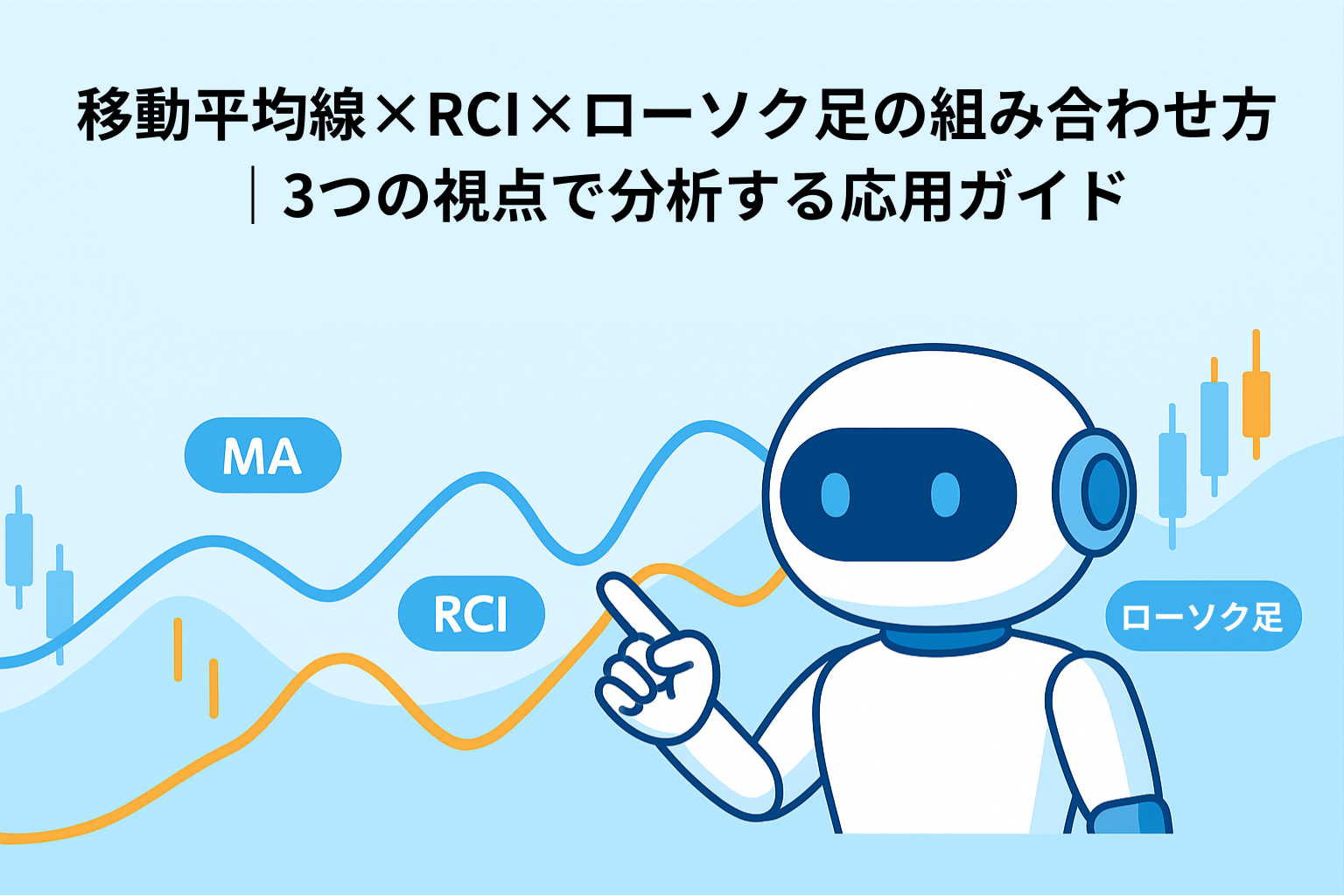
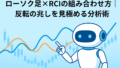
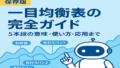
コメント