本記事の対象:MTF分析の基礎(上位足で環境認識→下位足で執行)を理解し、さらに制度化・再現性向上・リスク一貫性の確立を目指す上級トレーダー。
免責事項:本記事は教育目的の一般的情報であり、特定の銘柄・通貨・取引の推奨ではありません。将来の成績を保証するものでもありません。自己責任でご判断ください。
目次
- 導入:MTFの本質と「情報過多」の罠
- 設計思想:上位足→下位足への「シナリオ伝播」
- 相関・逆相関・主従関係の見取り図
- ダウ理論×構造認識×MTFの接続
- ボラティリティ正規化:ATRを軸にした時間足整合
- レジーム判定:トレンド/レンジ/圧縮/拡散の四象限
- 実践シナリオ:3つの高期待値テンプレ
- リスク管理:多層SL/TPと時間足ハイブリッド決済
- 運用実装:裁量・半自動・EAの役割分担
- 検証設計:テスト条件・ログ・指標の作り方
- 上級者が陥る落とし穴と回避策
- まとめ:少数精鋭の時間足で一貫性を担保する
- 付録:チェックリスト & よくある質問
- 1. 導入:MTFの本質と「情報過多」の罠
- 2. 設計思想:上位足→下位足への「シナリオ伝播」
- 3. 相関・逆相関・主従関係の見取り図
- 4. ダウ理論×構造認識×MTFの接続
- 5. ボラティリティ正規化:ATRを軸にした時間足整合
- 6. レジーム判定:トレンド/レンジ/圧縮/拡散の四象限
- 7. 実践シナリオ:3つの高期待値テンプレ
- 8. リスク管理:多層SL/TPと時間足ハイブリッド決済
- 9. 運用実装:裁量・半自動・EAの役割分担
- 10. 検証設計:テスト条件・ログ・指標の作り方
- 11. 上級者が陥る落とし穴と回避策
- 12. まとめ:少数精鋭の時間足で一貫性を担保する
- 13. 付録:チェックリスト & よくある質問
- 参考リンク
1. 導入:MTFの本質と「情報過多」の罠
マルチタイムフレーム分析(MTF)は、異なる時間軸の視点を統合し、「どの方向に、どれくらいの余地があり、どこで否定されるのか」を立体的に把握する技法です。上級レベルでの難しさは、時間足を増やすほど判断が遅れ、矛盾する情報が増え、結局のところ執行がぶれる点にあります。
- 本質:上位足の文脈(流れ・節目・リスク許容)を、下位足の執行に伝播して整合させること。
- 罠:月足〜1分足までを漫然と眺める「観光MTF」。意思決定が遅延し、過剰最適化や過度なフィルタリングに陥る。
原則:使う時間足は3〜4つに絞る。役割を明確化し、KPI(勝率・PF・平均RR・最大DDなど)を時間足別に分解して管理する。
2. 設計思想:上位足→下位足への「シナリオ伝播」
上位足は地図、下位足は拡大鏡です。最初に「どこからどこまでが優位性の射程か」を上位足で定義し、その範囲内でのみ下位足の戦術を許容します。
役割分担の例(4レイヤー)
- 週足:資金フローと主要レジーム(上昇/下降/レンジ)の同定。
- 日足:節目(高値・安値・中期MA・チャネル)の確定と「余地(上限/下限)」の見積もり。
- 4時間足:押し目・戻りの波形とトレンド継続/転換の分岐点。
- 15分/5分:執行の精度(エントリー/分割決済/失効条件)。
否定条件の先置き
上位足で否定ライン(シナリオが無効化される価格帯)を先に決め、下位足では「入る理由」より「入らない理由」を先にチェックする。執行ブレが激減します。
3. 相関・逆相関・主従関係の見取り図
「上位足に従う」は正しい一方で、転換期はしばしば逆相関が生じます。下位足の戻り売り/押し目買いが先行し、上位足の転換を先取りすることがあるためです。
- 主従関係:週足 > 日足 > 4時間 > 15分/5分。ただし転換初動は下位足から。
- 整合の基準:上位足の高安更新(ダウ)と、下位足の調整波の深さ(%・ATR倍率)を対比。
- 逆相関の活用:上位足レンジの上限/下限付近で、下位足の反転サインを拾う短期逆張り。
4. ダウ理論×構造認識×MTFの接続
ダウ理論は「高値安値の切り上げ/切り下げ」によるトレンド定義。MTFでは、上位足のダウ構造を下位足の小波動に分解して、どの波を取りに行くかを明文化します。
実装ポイント
- 日足で有効なダウ(直近スイング)を確定。
- 4時間足で同方向の中波動が継続しているかを検証。
- 15分/5分で「中波動の押し目/戻り」だけを執行対象に限定。
この階層化により、同じ「上昇トレンド」でも、どの部分を狙うのか(推進/調整/転換初動)をブレなく運用できます。
5. ボラティリティ正規化:ATRを軸にした時間足整合
時間足が違えば「同じpips」でも意味が変わります。そこでATRなどでボラを正規化し、上位足と下位足の指標を比較可能にします。
| 用途 | 指標 | 設定例 |
|---|---|---|
| 損切り | ATR×k | 15分:1.2〜1.8 / 4時間:2.5〜3.5 |
| 利確第一目標 | MAE/MFE比×ATR | MFE≧SLの1.2〜1.5倍 |
| トレード無効化 | 上位足ATR閾値 | 上位足ATR急縮小時は見送り |
コツ:SL/TPを「pips固定」ではなく「時間足ATR倍率」で統一。これにより相場環境の変化に順応しやすくなります。
6. レジーム判定:トレンド/レンジ/圧縮/拡散の四象限
レジーム(相場状態)を見誤るとシグナルは機能しにくくなります。MTFでは、上位足でレジームを先に定義し、下位足の戦術を切り替えます。
- トレンド×拡散:順張り。押し目/戻りからの推進波狙い。
- トレンド×圧縮:ブレイク待機。ダマシ回避のためトリガー厳格化。
- レンジ×圧縮:レンジ下限/上限での逆張り短期回転。
- レンジ×拡散:上位足レンジ内の中期トレンドに便乗。
7. 実践シナリオ:3つの高期待値テンプレ
シナリオA:王道の押し目買い(順張り)
- 日足:高値安値の切り上げ継続、主要MA上。
- 4時間:調整下落→中期MA(20/50)やチャネル下限に接触。
- 15分:反転サイン(スイング高値更新/包み足/モメンタム回復)。
執行:反転確定で分割エントリー。SL=15分ATR×1.5を基準に直近安値の外側。TP1=4時間の直近戻り高値、TP2=日足レジスタンス。
シナリオB:上位足レンジの端での逆張り(限定的)
- 日足:明確なレンジ。上限/下限が長期的に意識。
- 1時間:レンジ上限に過熱接近、ダイバージェンス。
- 5分:反転の小波動(戻り売り/押し目買い)が顕在化。
執行:上限反転を確認後に短期で逆張り。SLはタイト(5分ATR×1.2)。利確は日足レンジ中央〜対辺まで段階的に。
シナリオC:圧縮→拡散のブレイクフォロー
- 日足:ボラ縮小(ATR減少)、三角持ち合い。
- 4時間:レンジ内の高値・安値が徐々に切り上げ/切り下げ。
- 15分:出来高/モメンタムの拡大でレンジ外へ。
執行:ブレイク足の終値確定後に追随。失速なら即時撤退。
SL=ブレイク起点の内側、TPは日足の次節目まで段階利確。
8. リスク管理:多層SL/TPと時間足ハイブリッド決済
多層ストップの考え方
- 執行層:下位足の直近スイング外側(ノイズ誤差にATR×0.5〜0.8を上乗せ)。
- 構造層:4時間/日足の構造否定ライン(スイング否定)。
- ポートフォリオ層:同時相関ポジの総リスク上限(例:有効証拠金の0.5〜2%)。
時間足ハイブリッド決済
- TP1:下位足の直近節目で部分利確(リスク回収)。
- TP2:中位足(1H/4H)のターゲットで追加利確。
- TP3:上位足(日足)の節目までトレイル。
ブレークイーブン化:TP1到達でSLを建値+αへ。利確後に損切りへ転ぶ損益曲線を減らせます。
9. 運用実装:裁量・半自動・EAの役割分担
上級運用では「裁量判断」と「機械的一貫性」を棲み分けます。
- 裁量:上位足のレジーム判定、節目の質評価、ニュース/流動性イベントの影響度。
- 半自動:下位足でのトリガー検出、分割決済/トレーリングの自動化。
- EA:ルール化できる部分(時間足整合・ATR正規化・失効条件)の再現と記録。
結論としては「上位足=人、下位足=機械」のハイブリッドが、実務上の再現性と柔軟性を両立します。
10. 検証設計:テスト条件・ログ・指標の作り方
最低限のログ
- 時間足別のエントリー根拠(文章/タグ)。
- 入出場価格・SL/TP・ATR倍率・RR。
- MAE/MFE・保有時間・レジーム種別。
評価指標
- 勝率・PF・平均RR・最大DD・期待値(EV)。
- 時間足×レジーム別の分解(どこで勝っているか)。
- 「否定条件ヒット率」:無効化ラインでの撤退精度。
テストの落とし穴
- 上位足の節目を未来視してしまう「リーク」。
- 指標直後の異常値をフィルタせずに最適化。
- 複数時間足のデータずれ(確定足前提の整合性チェック必須)。
11. 上級者が陥る落とし穴と回避策
- 落とし穴:時間足を増やしすぎる → 回避:役割を3〜4層に限定、否定条件を先置き。
- 落とし穴:下位足の「綺麗な形」に固執 → 回避:上位足の余地と否定の整合を最優先。
- 落とし穴:SLが構造外に置けていない → 回避:構造層SLと執行層SLの二重化。
- 落とし穴:ニュースイベント無視 → 回避:上位足での予定表確認とサイズ縮小。
12. まとめ:少数精鋭の時間足で一貫性を担保する
- 上位足で「余地」と「否定」を定義し、下位足はその内側だけで戦う。
- ATRでボラを正規化し、時間足間の指標を比較可能にする。
- レジームに応じてテンプレ戦術(順張り/逆張り/ブレイク)を切替。
- 多層SL/TPと分割決済で、損益曲線の凹みをコントロール。
- 検証では「時間足×レジーム×否定条件」を必ず記録・分解。
13. 付録:チェックリスト & よくある質問
出陣チェックリスト
- 週足/日足のレジームは定義済みか(上昇/下降/レンジ/圧縮/拡散)。
- 否定ラインはどこか(価格/時間/イベント)。
- 4時間の中波動と日足の方向は整合しているか。
- 下位足トリガーは「上位足内側」でのみ有効化されているか。
- SL/TPはATR倍率で整合性が取れているか。
- イベント前後のボラ異常に対するルールはあるか。
よくある質問
Q. 時間足は何個使うのが最適?
A.原則3〜4個。役割が重複したら削る。迷いはコストです。
Q. 下位足だけで完結させたい。
A.可能ですが、上位足の否定ラインがないとシリーズ損失が増えやすい。少なくとも「日足または4時間」の節目は参照を。
Q. 逆相関の初動を取りに行くリスクは?
A.短期の優位性は高い一方、上位足に飲み込まれるリスクが常在。サイズ縮小・時間制限・素早い撤退で制御します。
Q. 最後は何が勝敗を分ける?
A.一貫性。設計した否定条件を守り抜く執行規律と、ボラ正規化に基づくサイズ管理です。
ポリシー配慮:本記事は教育的内容であり、過度な収益主張や具体的な投資助言を避ける表現に努めています。
参考リンク
本記事の内容理解に役立つ公式サイトへのリンクです。

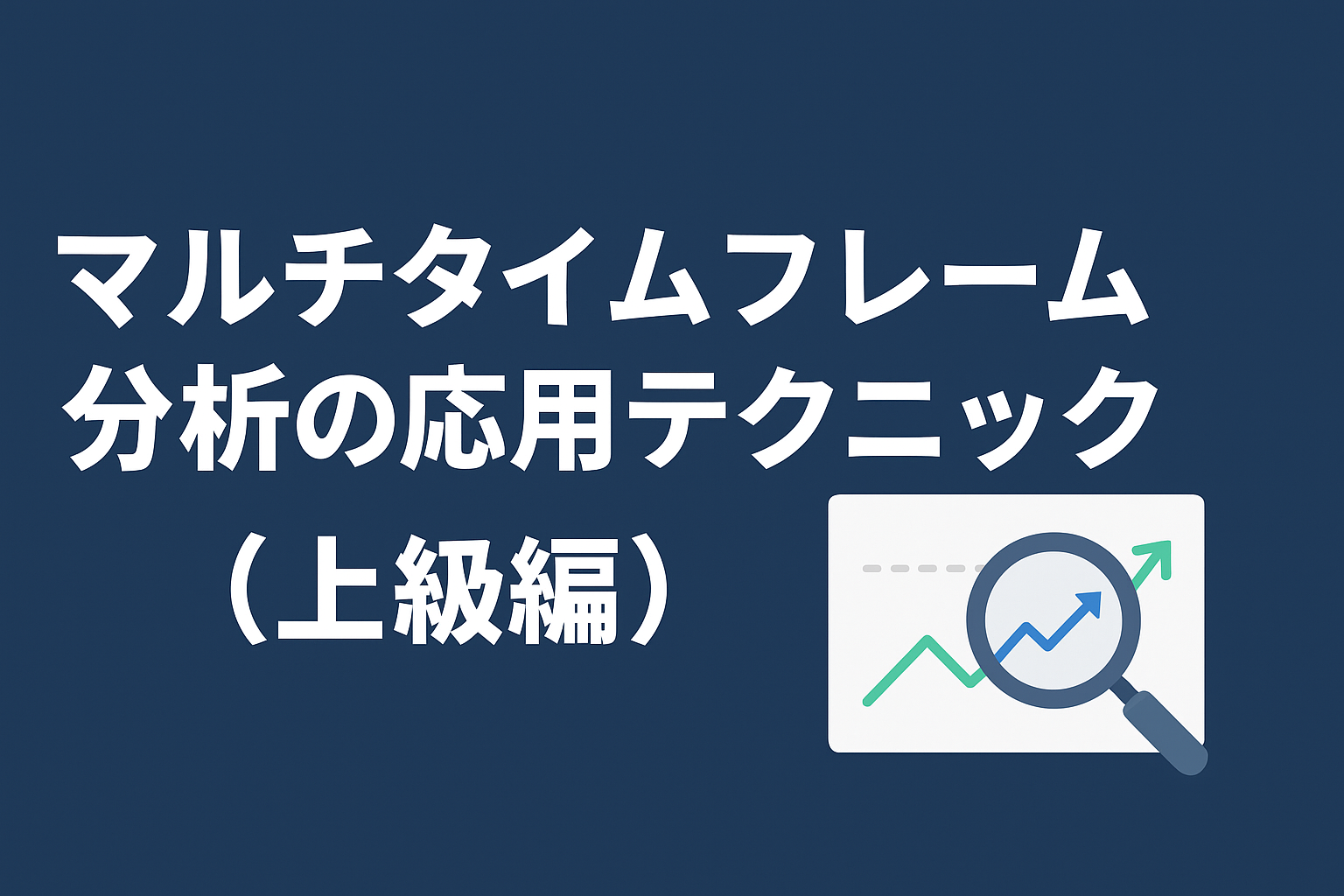
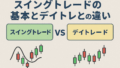
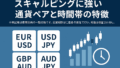
コメント